どうも!ケイトです!
世界史の用語って分かりづらい言葉のオンパレードですよね。今回は靖康の変と靖難の役です。区別つきますか?私も受験生時代、よくこんがらがりました。
ということで今回はそれぞれの解説と覚え方をお伝えしていきます!
Contents
靖康の変

靖康の変は、北宋の時代に起こった出来事でしたね。遼を滅ぼした金が、北宋の都である開封を包囲したことから始まりました
このことにビビって、さらに責任を感じた徽宗は、息子である欽宗に帝位を譲ります。息子の欽宗は金に、
「金銀と領土あげるから、帰ってくれえ!」とお願いしました。
金は、「まあそういうことなら」と言って、北に引き返していきました。
しかし、このまま一件落着、、、、かと思ったら、なんと欽宗は、全然約束を守りませんでした。
まさかの契約不履行www
まあこれには理由があって、この時は、貴族達が娯楽に税金を使いすぎたことで不況で、金銀がなかったからなんですね。
「約束どうなっとねん!」と借金取りばりにキレた金は、都の開放を占領するばかりか、上皇である徽宗と、皇帝である欽宗を拉致。
こうして、開封はまもなく陥落し、金は、宋にあった金銀財宝を一切合切持っていきました。そして、北宋はこのタイミングで滅亡します
あ、ちなみに、靖康というのは当時の年号で、今の「令和」みたいなものです。
変というのは、仕掛けた側が勝った時に使う字です。今回は金が勝ったも等しいので、靖康の乱ではなく、靖康の「変」ですね。
その後、命からがら逃げ出してきた皇族、高宗が宋を再建します。この宋は北宋と区別して、「南宋」と呼ぶんですね。
靖難の役

靖難の役は明の時代に起こった出来事でしたね。
初代の皇帝である洪武帝が没すると、次の皇帝を決めなければなりませんが、長男はこの前に亡くなってしまいました。
そこで皇帝になったのが、その長男の息子です。彼は建文帝になります。
洪武帝からしたら孫にあたりますね。しかし、ここで反発する人達がいます。洪武帝の息子達です。建文帝からしたら叔父さん達。
その叔父さんたちの中でも、闘志が素晴らしかったのが、末っ子である人物でした。彼は4人兄弟の末っ子で、皇帝になれる確率って低いんですよね。
建文帝は、皇帝の権威を高めようと、有力者の排除を行います。叔父さん2人も排除され、いよいよその末っ子がキレます。
叔父と甥の戦いとなります。この戦争は終わるまでに4年間もかかります。激闘の末、都である南京が陥落し、建文帝が敗れて自殺します。
勝った叔父さんは「永楽帝」となりました。
彼は戦いの時に、
「君側の奸を除き、帝室の難を靖んずる」、(建文帝の側近の奸臣をとり除き朝廷の危機を乗り切る)
ということを掲げたので、「靖難」という文字が使われています。
政治状況が悪くなると、政府が悪い!トップが悪い!ということを指していたのですが、名指しで「皇帝が悪い!」という風に言うと、それはもはや革命になってしまいます
武力を使って帝位を奪うことはあまり好ましくなかったので、革命は歓迎されませんでした
そこで、「皇帝の側近に悪いやつがいるから、政治も悪くなるんだ!」と言い換えることで、反乱を起こそうとしたわけですね。
それが、「君側の奸を除き」の意味です。
そうして、このような悪い政治状態に直面している朝廷が、側近を排除することで危機を乗り切って、国を治めよう!というのが、「帝室の難を靖んずる」の意味ですね
この言葉の中の「靖難」の2つの文字が採用されて、靖難の役と呼ばれているわけです
ちなみに、役は戦争という意味で、仕掛けた側が勝ったので、「靖難の変」とも呼ばれます。
覚え方
靖康の変と靖難の役。違いや名称の成り立ちについて分かりましたね。
成り立ちを思い出せば、こんがらがることもなくなります。ただ、思い出すきっかけはあればあるほどいいので、最後にダメ押しで、こじつけを紹介しますね。
せいこうのへん→こうと宋(そう)
(どっちも「う」で終わる)
せいなんのえき→せいなんと明(みん)
(どっちも「ん」で終わる)
まとめ
いかがでしたか?
それぞれの解説と覚え方をお伝えしました。これでこんがらがることがなくなりますね。
違いシリーズの他の記事も併せてご覧下さい。
ここでお知らせ!
世界史の勉強法が分からない、成績が全く上がらない、という人のために今だけ無料で「やみくもに暗記せずに世界史の偏差値を50から60した方法」を配布しています
ぜひゲットして、効率良く世界史の成績を上げていきましょう。
以下のボタンから、メルマガ登録して頂くと、手に入れることができます。
それでは!


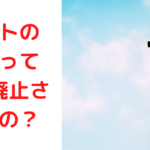


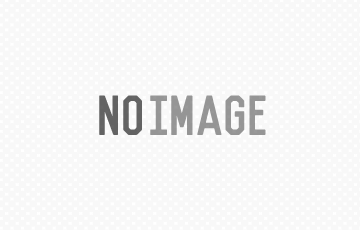




コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。