どうも!ケイトです。
世界史の勉強法を調べたときに、「世界史の流れを掴んで〜」なんて、よく言いますよね。でも、どうやって掴むかは結構曖昧だったりします。
ということで今回は世界史の流れを掴む方法をご紹介します。き
基本的にはインプットとアウトプットの繰り返しになります。それでは詳しく参りましょう。
Contents
読む
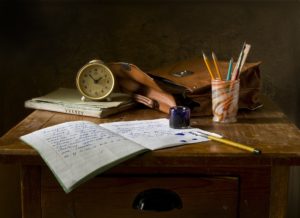
まずは歴史を全て読みます。全体像を見てみることが必要だからです。しかし教科書は表現が堅苦しいので、ナビゲーター世界史や実況中継、漫画などが良いと思います。
私はナビゲーターを使っていましたが、あなたが理解しやすいものでいいですよ。何度も読み返すことがミソです。
1周目
一周目はわからないところがあっても構わず進んでしまいましょう。
参考書をやるうえで、もっとも挫折しやすいのは一周目だからです。理解できていない部分が多すぎてつらいんですよね。時間もかかるし。
なのでわからないところはマークするなり印をつけて、とりあえず読み進めましょう。
プチ復習法
記憶に残すコツは、繰り返し復習すること。一度読んだあと次いつ読み返すか分からないし、時間が空くと忘れてしまいます。20分で大半を忘れ、1日経つともうほとんど覚えていないなんて話は有名ですね。
そこで、ちょっとだけ復習して、記憶に残りやすくしましょう。その名もプチ復習法
プチ復習の仕方は簡単です。これまで読んできたページをあるタイミングでパラパラパラ〜ッとめくるだけ。
こまめに確認して記憶を回復させることで、だんだんと頭に入ってきます。パラパラパラ〜ッとめくるだけなので、わりかし楽なのもポイント。試してみて下さい。
2周目以降
2周目は、1周目に印をつけた場所を理解してみましょう。よく考えてわからなければ、スルーしてしまって下さい。
重要用語になっているような出来事は何故起こったのか、その後どうなったのかなど整理してみます。
アンダーラインをひいて、それを線でつないでみて下さい。つながりが分かるようになってきます。
3周目も同じようにやり、さらっと3周が完了したら次のステップです。
ナビゲーター世界史には、巻末に小冊子がついていて、穴埋め問題ができます。これは利用しない手はないですね。各章を読み終わるごとにチェックテストとしてやってみましょう。シートで隠して繰り返しできるので、赤ペンで書くのがおすすめです。プチ復習法と組み合わせてやれば、定着が早くなります。勉強のポイントはアウトプットとインプットの繰り返しですからね。
読んだあとでもすっかりわすれちゃうときの解決法
はい!問題集といって問題を解きだしても、あれ、なんだっけ、読んだはずなのに思いだせねえってなったことありませんか?
読み流して理解はしたものの、問題を解く頃にはすっかり忘れてしまっている、というあれですね。私も、時間が無駄になってしまった、、、、と嘆いたりしました。
しかし、そんな悩みも一瞬で解決できる方法をお教えしましょう。それが、クイズ作りです。
これ重要そう、とか、あ理解できた、ってところを自分で問題にして残しておく。これだけ。
一番効率が良いと感じたのは、iPadのGoodnotes5というアプリで、単語カードをつくり、朝一番で問題を解いて復習をする、という方法です。
朝だから脳みそが疲れていないし、iPadだから紙の単語カードやノート、ファイルなどをわざわざ出してくる手間も省けます。時短で効率的なので、タブレットを持っている人は試してみて下さい。
読んでるだけだと頭に入らないというのは、ぶっちゃけ当たり前なんです。だって頭使ってませんからね。まとめノート眺めてるのと変わりません。
ですから、しっかり脳に負荷をかけることで、頭に残しやすくするわけです。簡単で効果抜群ですので、ぜひやってみて下さい。
問題を解いてみる

結構頭にはいったんじゃね?というタイミングで問題を解いてみます。一問一答形式でもいいですし、ハードルが高いなと思う人は、穴埋め形式のものを使いましょう。
なるべく薄めのものが良いです。つまり最低限の重要単語です。流れをつかむのが目的なので、細かすぎる知識は今は必要ないです。
分厚い問題集に苦戦して、せっかく読んだ内容を忘れたら意味が無いですし、最初から使うと挫折します。
分厚い一問一答は、薄めのものが終わり、流れも掴めてからやれば良いです。それに薄めの問題集でも、これは完璧だという確信が持てれば、自信になります。
薄めの問題集の使い方
これはシンプルです。問題を解き、正解したら丸をつけます。そして、丸が3つつくまで繰り返して下さい。問題集は薄いので周回は楽だと思います。
丸が3つついたものはさらっと見て復習して下さい。
漢字は書けないけど、答えは分かるというものは、単語カードに書いておきましょう。表はひらがなで、裏は漢字で。そうすると頻繁に復習できて便利です。
世界史用語は見て覚える?書いて覚える? マジで効率悪いのはどっち?!
繰り返す
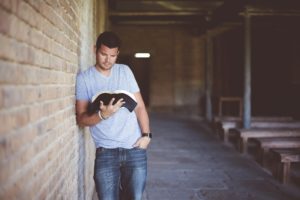
問題集も完了したら、読み物に戻ります。問題をやったうえで、分からなかったことや、あやふやだったところをもう一度確認していくのです。
わかるまで周回して下さい。
自分で説明できるくらいしっかり理解してあるところは、さらっと読み流し、苦手な部分を重点的にゆっくり読みます。緩急をつけて読めるようになるといいですね。
適宜問題集に戻ったり、必要な部分には印をつけたり付箋をつけたりしていくと、流れを掴んだ頃にはボロボロになっているでしょう。
流れが掴めたら、分厚い一問一答に進んで頂いて結構です。
まとめ
いかがでしたか?世界史の流れの掴み方について説明しました。しっかり周回と復習をして完璧にして下さいね。
それではまた会いましょう!








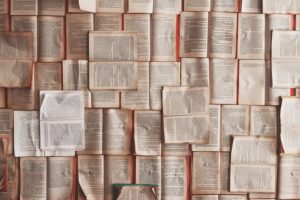

コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。